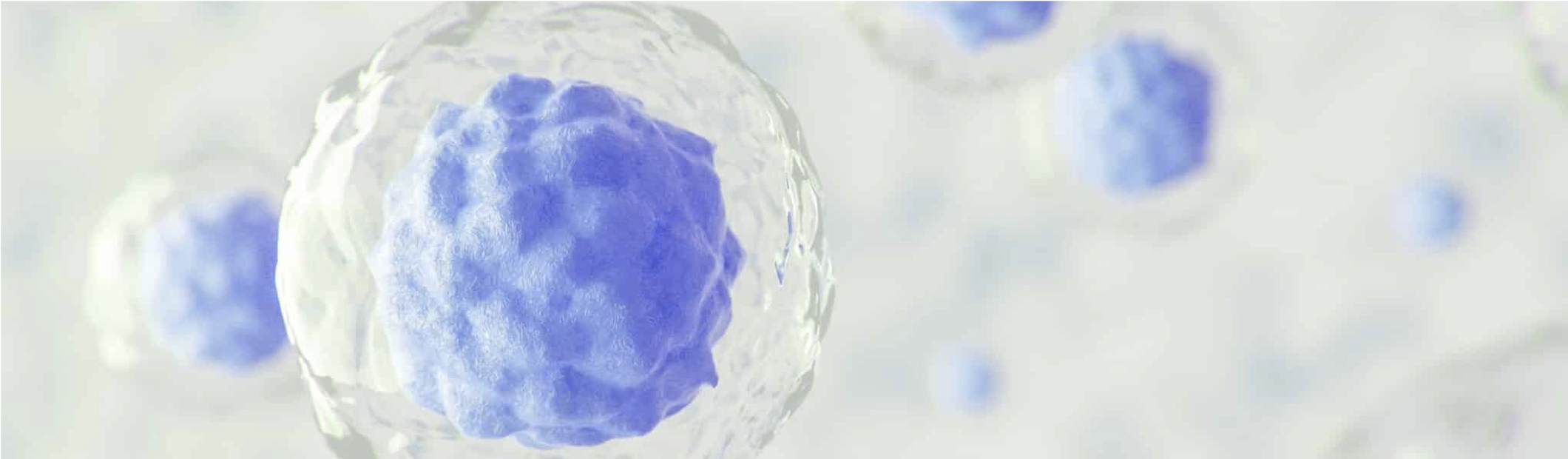脂肪由来間葉系幹細胞は、採取が容易で免疫原性が低く、再生医療において有望な細胞ソースとされています。中胚葉系以外への分化能力も有しており、加齢に伴いその数と機能が著しく低下することが知られています。これはテロメアの短縮やエピジェネティック変化が一因であり、こうした細胞の補充は抗加齢療法の科学的根拠ともなります。
● 代謝性疾患:2型糖尿病(膵島機能の改善)、脂質異常症、慢性腎疾患、高尿酸血症(痛風)
● 神経系疾患:脳梗塞後の神経機能障害、パーキンソン病、アルツハイマー病、脊髄損傷
● 循環器疾患:心筋梗塞、慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患(下肢虚血など)
● 消化器疾患:肝硬変、炎症性腸疾患(IBD)、膵機能障害
● 呼吸器疾患:慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息
● 免疫系疾患:関節リウマチ、全身性エリテマトーデス(SLE)�
● 運動器疾患:変形性膝関節症、膝関節可動域制限